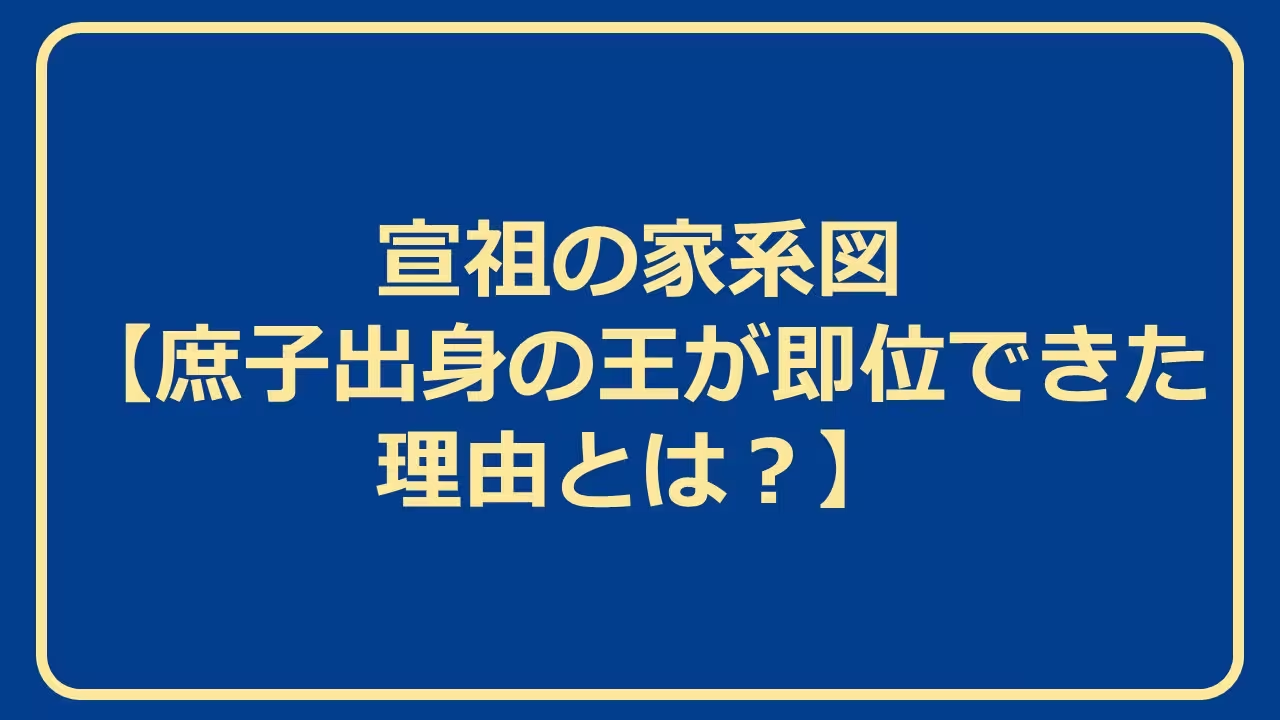王位から遠かった宣祖が第14代王になれたのはなぜか?
この記事では、宣祖の家系図をもとに、彼の即位の経緯と複雑な家族関係をわかりやすく解説します。
宣祖の家系図|王位から遠かった庶子の孫
宣祖は中宗の孫にあたりますが、直系ではなく、本来であれば王位から程遠い側室の傍系から生まれました。父は徳興大院君、母は河東府大夫人鄭氏です。
本来であれば王位継承の対象ではありませんでしたが、先王の明宗との特別な人間関係が即位を可能にしました。

当サイト「雲の上はいつも晴れ」が独自に作成した家系図
<宣祖の家系図>
【PR】スポンサーリンクなぜ庶子の孫が王に?|誕生した経緯
第13代王・明宗は一人息子・順懐世子を13歳で早世。側室にも跡継ぎがなく、王統は途絶える危機にありました。そこで注目されたのが、義弟・徳興君の三男・河城君(後の宣祖)でした。
明宗の母・文定王后と、河城君の祖母・昌嬪安氏は非常に親しい間柄で、昌嬪安氏の家系は王室から特別な存在と見なされていました。
特に、明宗は河城君をこの上なく可愛がっており、明宗の死後、王妃・仁順王后は彼の意をくみ、河城君を養子とし迎えています。こうして宣祖は庶子出身ながら王位に就くことになりました。(燃藜室記述 巻十二、宣祖朝、故事本末、宣祖入掌大統)
【PR】スポンサーリンク宣祖が即位したときの時代背景
宣祖の祖父・中宗はクーデターで王位に就いたため、臣下の力が強く、王権は形骸化していました。
中宗の晩年から仁宗、明宗の時代を通して、中宗の継妃・文定王后とその一族が政権を握り、朝廷を掌握していきます。宣祖が即位したときには、王室は形式的な存在となっており、王権は大きく弱体化していました。
また、宣祖の即位後、朝廷内では儒教の解釈や対外政策をめぐって官僚たちが対立し、やがて東人と西人に分裂します。これが後の党争激化のきっかけとなり、宣祖の治世を通して王権がさらに不安定化する一因となりました。
宣祖の人物像|学問重視の政策
宣祖は子供の頃から頭もよく、常に書物を傍に置くほど学問を好み、絵画や書道に造詣が深かったといわれています。そのため、即位後には李退渓や李栗谷などの儒学の大家を人材として登用し、学問を重視する政策をとりました。
「儒先録」や「三網行実」など多くの書物を刊行して儒家の発展に寄与しています。
生年:1552年11月11日
没年:1608年2月1日
享年:57歳
在位:1567年8月7日-1608年3月17日
姓・諱:李昖(イ・ヨン)(初名:鈞)
廟号:宣祖
父:徳興大院君
母:河東府大夫人鄭氏(鄭世虎の娘)
陵墓:穆陵
宣祖の廟号は、当初、「宣宗」でしたが、壬辰倭乱での貢献を評価して、正祖のときに「宣祖」に格上げされています。
宣祖の家族
宣祖には2人の正室と9人の側室の間に14男11女の子供をもうけました。
<王妃と代表的な側室と子供たち>
| 関係 | 名前 | 子女数 | 子供 |
| 正室 | 懿仁王后 | 子女なし | |
| 仁穆王后 | 1男2女 | 貞明公主、幽閉 | |
| 永昌大君(李㼁)、処刑 | |||
| 公主(早世) | |||
| 側室 | 恭嬪金氏 | 2男 | 臨海君(李珒)、処刑 |
| 光海君(李琿)、第15代王 | |||
| 仁嬪金氏 | 4男4女 | 義安君(李珹) | |
| 信城君(李珝) | |||
| 定遠君(李琈)、仁祖の父 | |||
| 貞慎翁主 | |||
| 貞恵翁主 | |||
| 貞淑翁主 | |||
| 義昌君 | |||
| 貞安翁主 | |||
| 貞徽翁主 |
このように、宣祖は多くの妃・側室との間に多くの子供をもうけましたが、特に光海君と永昌大君の間で起きた後継争いは、朝鮮王朝に深い亀裂を生む大事件となりました。
宣祖の二人の王妃
宣祖には二人の王妃がいました。
継室: 仁穆王后金氏
懿仁王后(ウイインワンフ)
懿仁王后は1569年に14歳で宣祖に嫁ぎましたが、子供には恵まれず、後に側室の子供である光海君を養子にしました。
宣祖は、2度に渡る日本からの侵略(壬辰倭乱、丁酉倭乱)に避難を続け、同行した懿仁王后は、1600年に体調を崩して亡くなりました。
仁穆王后(インモクワンフ)
仁穆王后は懿仁王后が亡くなったあとに、19歳で宣祖と結婚します。1606年に待望の王子である永昌大君を生みますが、党派の争いに負けて光海君が即位しました。
光海君即位後、宣祖の嫡子・永昌大君は流刑後に殺害され、仁穆王后の一族は粛清、さらに仁穆王后と娘の貞明公主は、西宮(ソグン)に幽閉されています。
宣祖の最も寵愛を受けた側室
宣祖には9人の側室がいました。その中でも、恭嬪金氏と仁嬪金氏が最も寵愛を受けた側室です。
恭嬪金氏(コンビン キムシ)
恭嬪金氏は宣祖に最初に寵愛を受けた側室でした。臨海君と光海君を生みますが、光海君を産んで2年後に亡くなりました。
仁嬪金氏(インビン キムシ)
仁嬪金氏は恭嬪金氏の死後、宣祖に寵愛された側室です。宣祖の寵愛を独占して、生涯に4男5女の子供を産んでいます。
1608年に宣祖が亡くなると宮殿を離れ、5年後の1613年に59歳で亡くなりました。
壬辰倭乱と宣祖の評価
1592年、日本の朝鮮侵攻が始まると、宣祖は王宮を捨てて避難。これが民衆の信頼を大きく損なう結果となりました。
逃亡劇の全貌はこちらで>>宣祖の生涯【壬辰倭乱の逃避に見る王の責任】
1608年、宣祖は特に目立った政治的業績を残すこと亡く、その生涯を閉じています。
宣祖が登場するドラマ
宣祖は多くの韓国時代劇ドラマに登場しています。特に、壬辰倭乱や光海君を描いた作品に多く登場しています。
・ホジュン 宮廷医官への道
(1999年、パク・チャンファン)
・王の女(2003年、イム・ドンジン)
・王の顔(2014年、イ・ソンジェ)
( )内は演じた俳優
まとめ
宣祖は王位継承から遠い存在でしたが、王族間の特別な縁故によって第14代国王となった、初の庶子出身の王です。
しかし、宣祖の治世は壬辰倭乱や後継問題など、混乱と試練に満ちていました。
壬辰倭乱時の彼の行動は、民衆からの信頼を大きく失い、50歳を過ぎて得た嫡子は後継者争いで、朝鮮王朝の歴史に大きな影を落とすことになりました。