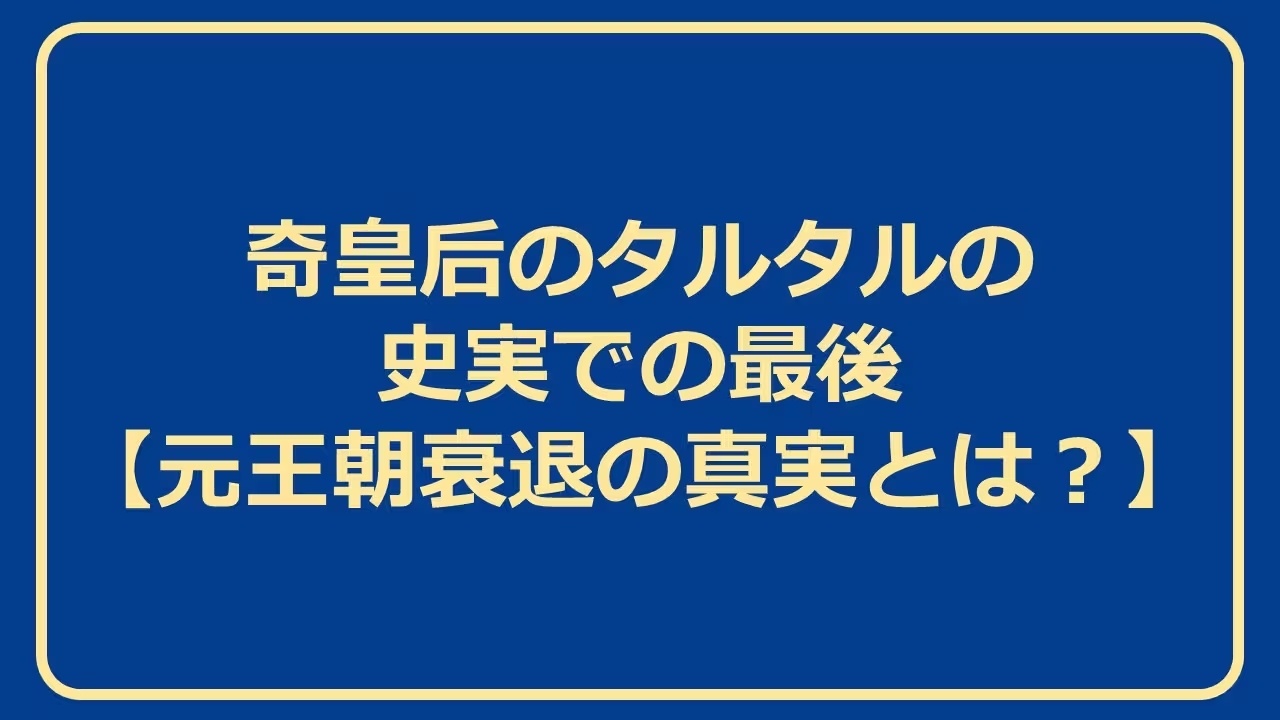ドラマ「奇皇后」で一躍人気を集めたタルタルは戦場で戦死します。しかし、タルタルのモデル・トクト(脱脱)の最期は皇帝トゴン・テムルの命による賜死でした。
この記事では、ドラマ描写と史実の違いを整理し、タルタル(トクト)の死が元王朝の衰退を早めた歴史的意味に迫ります。
ドラマと史実で異なるタルタルの最期
まずは、タルタル(トクト)の最期をドラマと史実で簡単に比較します。
・ドラマ「奇皇后」:紅巾軍との戦で壮絶な戦死
・史実:トゴン・テムルの命で毒薬による処刑
ドラマで戦死したタルタルですが、史実では1354年、紅巾の乱の鎮圧に向かう途中で失脚。皇帝トゴン・テムル(タファンのモデル)によって職務を解任され、流刑地への護送中に毒薬により殺害されています。
タルタルの死は、単なる武将の最期ではなく、元王朝の運命そのものを揺るがす出来事でした。
【PR】スポンサーリンクタルタルの失脚と元王朝の衰退
トゴン・テムルは有能な丞相タルタル(トクト)の権勢を恐れ、ついに自らの手で処刑に追い込んだのです。
タルタル(トクト)という名将を失った元の軍隊は次第に弱体化していきました。結果として紅巾の乱は収束せず、やがて明の建国につながります。
これが、明の侵略を許し、元の滅亡を早めていく直接の要因となりました。
【PR】スポンサーリンク奇皇后・タファンとの関係
ドラマでは、タルタル(トクト)は奇皇后に一目置きつつも距離を保ち、暴走する伯父ペガンを何と正しい道に戻そうと苦悩する「孤高の武将」として描かれています。また、視聴者には「最終的には奇皇后を支えた存在」との印象が残りました。
しかし史実では、奇皇后やタファンと親しい関係を築いた記録はほとんどありません。むしろ権力闘争に巻き込まれ、最後はタファン(トゴン・テムル)により毒殺されています。ドラマでの英雄的な描写とは大きな違いあります。
紅巾の乱とタルタルの政策
紅巾の乱は1351~1366年に起きた農民反乱で、元王朝崩壊の直接のきっかけとなりました。その背景には、タルタル(トクト)が実施した紙幣の大量発行や黄河の治水工事など、民衆に重い負担を強いた政策がありました。
乱発した紙幣による経済混乱と工事負担による農民の怒りは宗教結社の煽動に結びつき、大規模な反乱を引き起こしました。
家系図で知るタルタルの人物関係
ドラマでタルタルはペガンの甥でしたが、実在したトクトも宰相バヤン(伯顔)の甥にあたり、幼い頃に養子になっています。

当サイト「雲の上はいつも晴れ」が独自に作成した家系図
<タルタル(トクト)の家系図>
実在したトクトの人物像
タルタルのモデルであるトクトは元を支えた政治家であり名将でした。トクトの父親マジャルタイも元の第3皇帝カイシャンに大変信頼された武将でした。
トクトのプロフィール
元史には
「国家のために奉仕し、非常に人間的でおごりがない大臣である。お金や財産に執着せず、色恋は好まず、徳と礼を重んじた。」
と記録されています。
漢字表記:元史は脱脱、清代以降は托克托
脱脱の韓国語読み:タルタル
生年:1314年
没年:1355年
部族:メルキト族
父親:マジャルタイ(馬札児台)
長男:哈剌章
次男:三宝奴
伯父(父の兄):バヤン (伯顔)
トクトの生涯年表
トクトの生涯を出来事も合わせて整理しました。
| 年 | 出来事 |
| 幼少時 | バヤンの養子になる |
| 1328年 | 皇太子のアリギバ(第11代皇帝)に仕える |
| 1333年 | エル・テムル逝去。トゴン・テムルが皇帝になる |
| 1335年 | バヤンが権力掌握、暴政を行う |
| 1340年 | トゴン・テムルと共にバヤンを追放、宰相となる |
| 1340年 | 科挙を復活させる |
| 1343年 | 「金史」、「遼史」、「宋史」の歴史書を編纂 |
| 1351年 | 紅巾の乱が勃発。10万の兵で鎮圧する |
| 1354年 | 再度、紅巾の乱の鎮圧に向かう途中に失脚。賜薬による死罪 |
| 1362年 | トクトの名誉が回復される |
まとめ
ドラマ「奇皇后」でタルタルは英雄的戦死として描かれますが、史実のモデル・トクトは皇帝トゴン・テムルの命で処刑された権力闘争の犠牲でした。
その死は奇皇后やタファンの権力関係にも影響し、最終的に元の衰退と明の侵略を許すことになります。
タルタルの最期は、まさに一人の武将の死が王朝の命運を左右する歴史的事件だったのです。