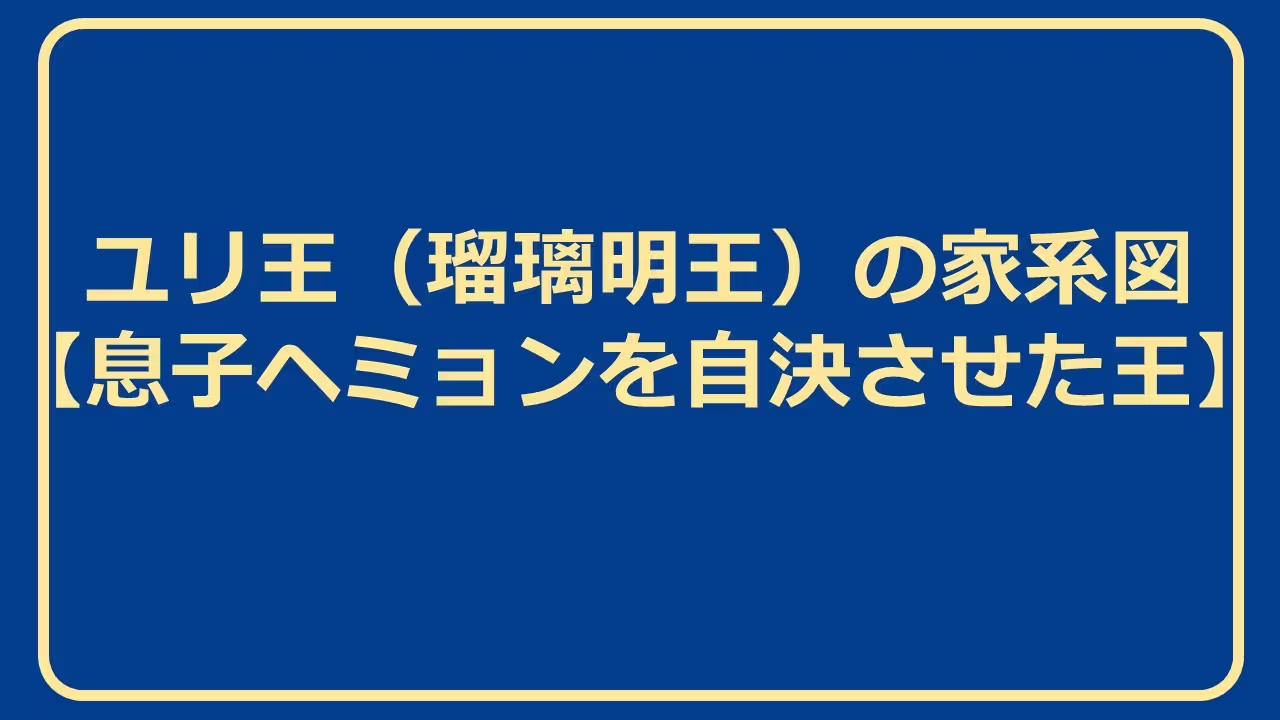ユリ王(瑠璃明王)チュモン(東明聖王)の息子で高句麗の第2代王です。
この記事では、「三国史記」と「三国遺事」の家系図の違い、息子ヘミョンを自決させた悲劇、ドラマ「風の国」と史実の違いを詳しく解説します。
ユリ王の家系図
ユリ王(瑠璃明王)はチュモン(東明聖王)と最初の妃・礼氏夫人との間に生まれました。
異母弟にはチュモンと召西奴(ソソノ)の間の生まれた沸流(ピリュ)と温祚(オンジョ)がいます。後に、温祚は召西奴と沸流と共に高句麗を離れ、百済を建国しています。
「三国史記」と「三国遺事」では少し系図が異なります。次は、三国史記による家系図です。

当サイト「雲の上はいつも晴れ」が独自に作成した家系図
<三国史記によるユリ王の家系図>
五男の解色朱(ヘセクチュ)は第4代王・閔中王です。第3代王・大武神王の息子が幼かったため、王に推挙されたと記録されています。
六男の再思(チュサ)の息子は第6代王・太祖大王です。ただし、この継承は王統が断絶しないように別の血筋から編入させたとする説もあります。
次に三国遺事による家系図をご紹介します。

当サイト「雲の上はいつも晴れ」が独自に作成した家系図
<三国遺事によるユリ王の家系図>
「三国遺事」では、閔中王は大武神王の子であり、第5代王・慕本王は閔中王の弟と記されています。明らかに史料間での食い違いが見られます。
【PR】スポンサーリンクユリ王はどんな王だったのか?
ユリ王が即位した時期は、高句麗の周りは沸流國、鮮卑、扶余などの強国に囲まれ、内政も不安定な時期でした。
それにもかかわらず、ユリ王は狩猟に熱中。そのことを諌めた重臣を罷免するなど、王としての資質に欠ける面がありました。
在位期間:BC19年-AD18年
都城:紇升骨城→国内城
諱:類利(ユリ)または解儒留
諡号:瑠璃明王
生年:BC37年
没年:AD18年10月(享年56歳)
ユリ王の呼び名(表記)
ユリ王の呼び名に関しては史料ごとに異なる表記が残されています。
| 史料 | 表記 |
| 「三国史記」高句麗本紀 | 琉璃王、琉璃明王 |
| 「三国遺事」王暦 | 瑠璃王 |
| 「広開土王碑文」 | 儒留王 |
| 「魏書」高句麗伝 | 閭達(リョダル) |
ユリ王の家族
ユリ王は多勿国王・松讓の娘を正室として、複数の妃を迎えました。記録には6男1女の子供の名前が記されています。
| 関係 | 名前 | 生年-没年 | 備考 |
| 正室 | 松氏 | 不詳-BC17 | 多勿の国王・松讓の娘 |
| 長男 | 都切(トジョル) | BC17-AD1 | |
| 継室 | 松氏 | 不詳 | 前妻の姉妹、第二王妃 |
| 次男 | 解明(ヘミョン) | BC12-AD9 | 自決 |
| 長女 | 不詳 | 不詳 | 羽氏の妻 |
| 三男 | 無恤(ムヒュル) | AD4-AD44 | 第3代王・大武神王 |
| 四男 | 如津(ヨジン) | 不詳-AD18 | 溺死 |
| 五男 | 解色朱(ヘセクチュ) | 不詳-AD48 | 第4代王・閔中王 |
| 継室 | 不詳 | 不詳 | 第三王妃、再思の母 |
| 六男 | 再思(チュサ) | 不詳 | 息子が第6代王・太祖大王 |
| 継室 | 禾姫(ファヒ) | 不詳 | 鶻川人の娘 |
| 雉姫(チヒ) | 不詳 | 漢人の娘 |
断剣説話|チュモンの息子の証
ユリ王は幼少期、父チュモンが亡命していたため顔を知りませんでした。後に対面した際、剣の破片を示して自らがチュモンの息子であることを証明しています。
この「剣」の逸話はドラマにも描かれ、朝鮮神話の「三種の神器」の一つとされています。
義兄弟の百濟建国
第二夫人となった召西奴はユリ王の義弟・沸流(ピリュ)と温祚(オンジョ)をつれて高句麗を離れていきました。BC18年、温祚は百濟を建国して初代王に就いています。
二人の妃の争い
ユリ王は正室・松氏の死後、鶻川人の禾姬(ファヒ)と漢人の雉姬(チヒ)を迎えましたが不仲で、東宮と西宮に分けて住ませました。
ある日、狩りで不在中に争いが起き雉姬が実家に帰ると、それを知ったユリ王は馬で追ったとされます。ユリ王が自ら迎えに行くほど彼女を深く寵愛していたのか、漢との関係を重んじたのか、今となっては定かではありません。
重臣・陜父(ヒョッポ)の罷免
AD3年、国内城に遷都後、重臣の陜父(ヒョッポ)がユリ王の政務怠慢を諫めました。すると、ユロ王は激怒。陜父を罷免してしまいます。陜父はこれを機にユリ王のもとを去っていきました。
太子・解明(ヘミョン)の自決
ユリ王の説話の中で最も有名な話がこの解明(ヘミョン)を自決させた話です。ドラマ「風の国」では、テソ王の暗殺に失敗した解明がテソ王の前で自決していますが、これはフィクションです。
史実によると、隣国の黃龍王が解明に弓を贈りましたが、彼はこれを折って返しました。これを聞いたユリ王は激怒し自害を命じます。解明は高句麗が軽視されるのを嫌った行動でしたが、ユリ王は国交を優先しました。
解明は家臣の制止を振り切り槍に身を投じ21歳で命を絶ったとされます。
ユリ王の最期
AD18年10月、ユリ王(瑠璃明王)は豆谷の離宮で亡くなりました。跡を継いだのは三男の無恤(ムヒョル)で、第3代王・大武神王として即位しています。
まとめ
ユリ王(瑠璃明王)はチュモン(東明聖王)の息子として生まれ、内外とも不安定な高句麗を統治しました。外交を重んじたユリ王は力でねじ伏せる太子・解明(ヘミョン)を自決に追い込むなど厳格すぎる面もありました。
彼の治世は試練の連続でしたが、後を継いだムヒョル(無恤)が周辺国を次々と征服。高句麗は大きく飛躍します。ユリ王の系譜と生涯は、古代朝鮮史を語る上で欠かせない重要な一章です。